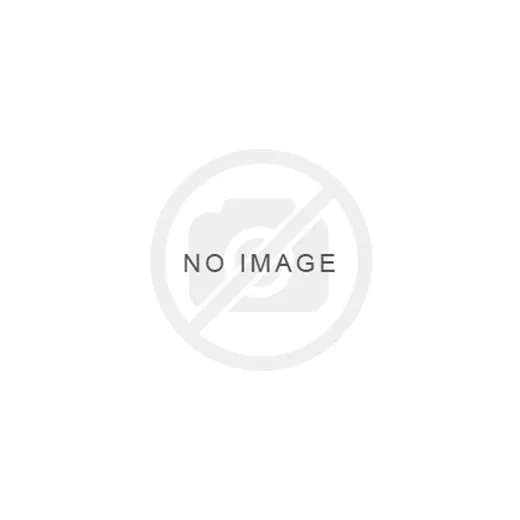ちょっと、そこ!熱電対ワイヤーサプライヤーとして、私はしばしば熱電対ワイヤのシーベック係数について尋ねられます。だから、私はこのブログ投稿でそれを分解すると思った。
基本から始めましょう。熱電対は、温度を測定するために使用されるデバイスです。一端に結合された2種類の金属ワイヤで構成されています。結合端(測定ジャンクション)ともう一方の端(参照接合部)の間に温度差がある場合、電圧が生成されます。これは、Seebeck効果が登場する場所です。
Seebeck効果は、1821年にThomas Johann Seebeckによって発見されました。彼は、2つの異なる金属が接続され、接合部に温度勾配があると、電流が流れることがわかりました。 Seebeck係数は、熱電力または熱負力とも呼ばれ、単位の温度差ごとに生成される電圧の量の尺度です。通常、シンボルα(アルファ)で示されます。
SeeBeck係数は、熱電対の感度を決定するため、重要です。より高いシーベック係数は、特定の温度差について、熱電対がより大きな電圧を生成することを意味します。これにより、特に小さな温度変化に対処する場合、温度を正確に測定しやすくなります。
現在、さまざまなタイプの熱電線が異なるSeeBeck係数を持っています。例えば、THEMRUCOUPLEワイヤと入力します銅とコンスタンタンで作られています。比較的高いSeeBeck係数を備えているため、温度変化に非常に敏感になります。このタイプの熱電対は、研究室や一部の産業プロセスなど、高精度が必要なアプリケーションでよく使用されます。
一方で、K Thermocoupleワイヤと入力しますクロメルとアルメルで作られています。これは、温度範囲が広く、その範囲で比較的安定したシーベック係数を備えているため、最も一般的に使用される熱電対の1つです。 -200°Cから約1372°Cまでのアプリケーションで使用できます。
SeeBeck係数は一定の値ではありません。温度によって異なる場合があります。ほとんどの場合、シーベック係数と温度の関係は非線形です。これは、温度が変化するにつれて、シーベック係数も変化することを意味します。これを説明するために、キャリブレーション曲線がよく使用されます。これらの曲線は、Seebeck係数が特定のタイプの熱電対ワイヤの温度によってどのように変化するかを示しています。
熱電対ワイヤを製造するときは、シーベック係数がワイヤー全体で一貫していることを確認するために細心の注意を払っています。 SeeBeck係数の変動は、測定エラーにつながる可能性があります。高品質の材料と正確な製造プロセスを使用して、これらのバリエーションを最小限に抑えます。
考慮すべきもう1つの重要なことはです熱電対拡張ワイヤ。これらのワイヤは、熱電対の長さを測定点から測定器に伸ばすために使用されます。拡張ワイヤには、正確な温度測定を確保するために、熱電対ワイヤと同じSeebeck係数が必要です。 Seebeck係数が一致しない場合、温度読み取りにエラーを導入できます。
熱電対ワイヤのシーベック係数を測定するには、特別なセットアップが必要です。通常、熱電測定システムを使用します。このシステムは、温度制御環境で構成されており、熱電対ジャンクション全体に既知の温度差を作成できます。次に、熱電対で生成された電圧を測定し、式α=ΔV/ΔTを使用してシーベック係数を計算します。ここで、ΔVは電圧の差、ΔTは温度差です。
現実の世界アプリケーションでは、Seebeck係数を理解することで、ジョブに適した熱電対ワイヤを選択するのに役立ちます。たとえば、非常に小さな温度変化を測定する必要がある場合は、高いシーベック係数を備えた熱電対ワイヤが必要です。ただし、広い温度範囲を扱っている場合は、その範囲でより安定したSeeBeck係数を持つ熱電対を選択できます。
熱電対ワイヤーサプライヤーとして、さまざまなアプリケーションニーズを満たすために、さまざまなSeeBeck係数を備えた幅広い熱電対ワイヤを提供しています。科学的実験、産業プロセス、DIYプロジェクトに取り組んでいるかどうかにかかわらず、適切な熱電対ワイヤがあります。
Thermocoupleワイヤの市場にいて、Seebeck係数、またはアプリケーションに最適なワイヤーのタイプに関する詳細情報が必要な場合は、お気軽にご連絡ください。私たちはあなたが正しい選択をし、あなたのプロジェクトで正確な温度測定を確保するのを手伝うためにここにいます。
参照
- NISTハンドブック150-熱電対標準とキャリブレーション
- DM Roweによる「Thermoelectric Handbook:Macro to Nano」